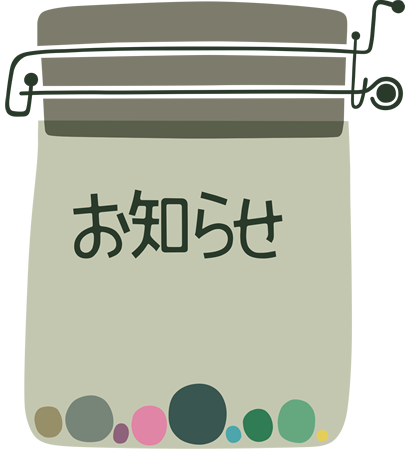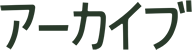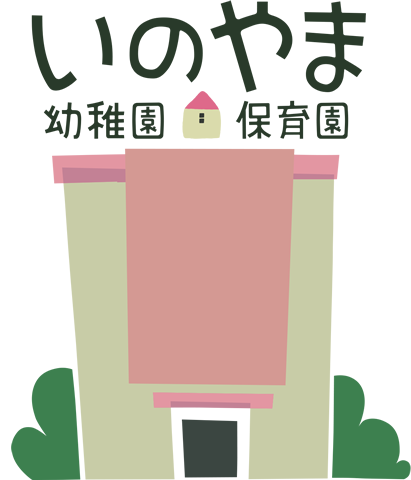2025.04.16
Category:放課後等デイサービス
【ジュニア】4/7(月)~4/12(土)活動報告
今週の活動報告は、今回はワークの学習の様子、学習後の様子についてお伝えいたします。
*****************************
【子どもたちの様子】
◆すらら
・ビーンズの学習時間では宿題に取り組んでからすららに取り組む子が多いです。
・今回は『いまなんじ?、いまなんじはん?』、『時刻と時間』のユニットについて紹介します。
〇『いまなんじ?、いまなんじはん?』
【ねらい】時計を見て、ちょうど何時か、いま何時半かわかるようになる。
すららではレクチャー→ゲーム→ドリルの順番で学習を進める形が多いです。
短い針が1、長い針が12をさしているイラストが出てきます。この時計は1時ということを確認します。
次に、時計の針が3時から4時に変化する時の時計の針の動き方を確認していき、長い針がぐるっと一周すると1時間進むことを確認していきます。
長い針が6をさしているときは「半」と言い、数字と数字の間にみじかい針がある時は、通りすぎた数字が「何時か」を表していることを確認していきます。
時計を見て、今何時かを回答していくゲームに挑戦します。
低学年の子はパソコンのキーボードの使い方を先生と一緒に確認しながら取り組んだり、「さんすうとけい」を使いながら時計の動き方を確認したりしながら取り組んでいます。
高学年の友だちが「一緒に教えてあげるね」と声をかけてくれたりする場面もたくさん見られます。
〇『時刻と時間』
ねらい:何時間か、何分かがわかるようになる。
時計のイラストで、短い針が2と3の間にある場合は2時●分ということを確認していきます。
次に長い針に注目し、長い針が4を3つ過ぎたところは何分になりますか?という問題が出題され、『●分』ということを確認していきます。
次に具体例として【3時におやつを食べ始めました】→【3時におやつを食べ終わりました】このようなものを『時刻』、時刻と時刻の間のことを『時間』と呼ぶことを確認していきます。
分からないところがある時は、先生に「わかりません」「教えてください」など、できるだけ自分から助けを求められるようにしています。
今後も一人ひとりの子どものペースに合わせて、一緒に確認しながら支援していきます。
◆学習後の時間も、子どもたちが集中して取り組める活動を準備しています。
紙に絵を描いたり、パソコンで描いたり、お絵描きを楽しむ姿があります。
「描画キャンバス」というアプリを使って、パソコンでのお絵描きに挑戦する子もいます。
「描画キャンバス」では、指やペンを使い分けて線の太さを変えたり、たくさんの色の中から選んだり、工夫しながら発想力豊かに取り組んでいます。
「ここはどうやって描いたの?」「上手だね!」と友だち同士で描いた絵を見せ合うなど、異年齢の交流も見られます。
先生や友だちとの関わりを深めながら、ビーンズが安心して過ごせる場所となるよう、支援していきたいと思います。
*****************************
【職員コラム】
先日、こちらで『小笠原諸島(父島)』の自然についてご紹介しましたので、そのお話のつづきをさせていただきます。
小笠原諸島は、小さい島でありながら小笠原でしか見ることのできない「固有種」の割合が高いことなどが評価され、世界自然遺産の4つの評価基準のうちの『生態系』の評価基準に合致するとして、平成23年に世界自然遺産に登録されました。
小笠原の生物は、鳥に運ばれたり、海流や風に流されたり、流木に付着したり、すべて何らかの方法で島に偶然たどり着き、島の環境に適応して生き残ったものの子孫です。
小笠原に定着できた種は、長い時間をかけて独自の進化の道を歩み、その中には小笠原諸島にしかいない「固有種」へと進化するものも出現しました。
私が以前、小笠原諸島に遊びに行った際には固有種の「アカガシラカラスバト」に遭遇しました!
後で宿のオーナーさんに聞いたら、「見れたらとってもラッキーなんだよ」と言われ、とてもうれしかったです☆
小笠原固有の生き物はとても貴重なものですが、小笠原に人が住み始めたことで本来小笠原にはいない生き物(外来種)が持ち込まれるようになりました。
小笠原固有の生き物の多くは、こうした外来種から身を守ることができず、大きな影響を受けています。
そのため、小笠原諸島では固有種を守る『小笠原ネコプロジェクト』など様々な活動が行われています。
その様々な活動についてはまた次回、私のコラムでお話します。楽しみにしていてください!
*****************************
最後までお読みいただき、ありがとうございました。